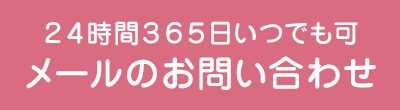婚姻要件不備の届出書受理婚姻の法文解説
本ページでは、婚姻についての法文を解説しています。離婚についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。
離婚・財産分与・慰謝料請求は、最低限の費用で済む当事務所へご相談ください。
婚姻届書は、要件具備を確認したうえでなければ、受理し得ない届書ですが、誤って受理した場合でも、婚姻意思がある限り、無効とはなりません。
民法第739条2項の届出方式に違反する場合は、効力は妨げられません(第742条2項)。
実質的要件を欠く場合(第731条~736条)には、取消自由となります(第744条)。
そして、その効果は、遡及しません(第748条1項)。
したがって、取消自由が消滅すれば、確定的に有効となります。
さらに、未成年者の婚姻につき、父母の同意を欠く場合については、取消事由ともされていませんから、受理によって、婚姻は有効に成立します。
受理要件を満たした届書が提出された場合、戸籍吏は、受理しなければなりません。
正当な理由なくこれを受理しない場合、当事者は家庭裁判所に対し、不服申立てができます。
そして、不服の申立てに理由があると判断された場合、市町村長は、この届出を受理しなければなりません。
届出は、受理により効力を生じますから、受理以前にこれを取り下げることは可能ですが、一旦受理された以上は、撤回し得ないとするのが、実務の先例です。
婚姻の届出が受理された場合、夫婦の新戸籍が編製されます(戸籍法第16条1項本文)。その場合、自己の氏を夫婦の氏として称する方が、戸籍の筆頭者となります(民法第750条、戸籍法第74条)。
ただし、自己の氏を称する夫または妻が、すでに戸籍筆頭者であるときは、他方がその戸籍に入籍します(戸籍法第16条1項ただし書・2項)。
夫婦の一方が、外国人の場合は、日本人について新戸籍を編製するが、その者が戸籍筆頭者である場合は、当該外国人が配偶者となる旨、その戸籍に記載されます(戸籍法第16条3項・6条)。