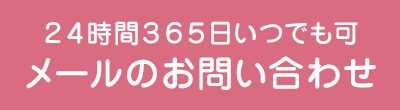婚姻届の代筆・口頭届出婚姻の法文解説
本ページでは、婚姻についての法文を解説しています。離婚についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。
離婚・財産分与・慰謝料請求は、最低限の費用で済む当事務所へご相談ください。
民法第739条
1.婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる
2.前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない
本条は、婚姻が届出によって成立すること、すなわち、わが国の婚姻方式は、届出婚主義であることを、宣言したものです。
届出地は、本籍地または所在地です。
書面による届出についての記載事項は、戸籍法および戸籍法施行規則により定められています。必要事項を記載し、届出人および証人が、署名押印をしなければなりません。
婚姻届では、代書ができるかが問題です。
判例は、養子縁組につき適用を肯定しています(最高裁判所判決昭和31年)。したがって、同じ創設的届出の婚姻届も、代書ができると解されています。
実務の取扱いも、理由を附記すれば、代書を認めています。
なお、原則が自署である以上、ゴム印、機器によるプリントなどは、認められないと解すべきです。
提出方法は、本人が作成した届出書は、他人が代わって提出することや、郵送することも可能です。
郵送については、特に規定があります。
それは、生存中に郵送した届書は、死亡後であっても受理しなければならず、受理されたときは、死亡の時に届出があったものと、みなされます(戸籍法47条)。
届出は、やむを得ない事情がある場合を除き、法定様式の書面で、届けなければなりませんが、例外的に、口頭ですることもできます。
口頭で届出をする場合は、当事者および証人の全員が、市役所または町村役場に出頭し、記載事項を陳述しなければなりません。市町村長は、これを筆記し、届出年月日を記載して、これを届出人に読み聞かせ、かつ届出人に、その書面に署名押印させます(戸籍法37条2項)。
当事者および証人の1人が書面で、他の者が口頭での届出はできません。
また、口頭での届出を、代理人が行うことはできません。