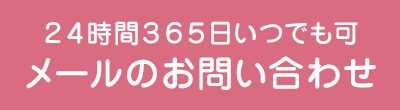重婚的内縁の法的保護婚姻の法文解説
本ページでは、婚姻についての法文を解説しています。離婚についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。
離婚・財産分与・慰謝料請求は、最低限の費用で済む当事務所へご相談ください。
重婚的内縁とは、内縁当事者の一方または双方に、法律上の配偶者のいる内縁関係です。内縁である以上、夫婦共同生活としての実体が不可欠です。その論理的な帰結として、法律上の夫婦関係は破綻し、形骸化していることになります。
なお、現実には、先の内縁関係の共同生活の実体が残存しながら、後の内縁関係の共同生活が、始まっていることもあります。排他的独占的な共同生活関係がなくても、住民登録や公的な場での妻としての扱いなどから、内縁が認定されれば、内縁が重複することがあり得ます。
判例は、死亡した男性の遺族共済年金の受給権を、二人の女性が、それぞれ内縁の妻として争った事案について、先行する内縁関係が実体を失っていない限り、先行する内縁関係を尊重して、その内縁の妻が、遺族共済年金の配偶者に該当するとしました(東京地方裁判所判決昭和63年)。
重婚的内縁関係にある男女の共同生活が、内縁として法的保護を受け得るためには、次の条件が必要です。
第一に、内縁当事者間に、婚姻意思と夫婦共同生活の実体が存在することです。
第二に、競合する法律婚が、実体を失って形骸化し、事実上離婚状態にあることです。
問題は、法律婚破綻の認定基準です。
判例は、婚姻秩序を維持し、法律婚の利益を優先するため、法律婚破綻の認定基準を、かなり厳しくしています。
わずかでも法律上の妻子との音信や交渉、生活費の支給などがあれば、破綻を認定しない傾向があります(広島地方裁判所判決昭和55年)。
他方、法律上の妻に、離婚意思がある場合には、法律上の妻への経済的給付を事実上の離婚給付と認定しています(最高裁判所判決昭和58年)。
要するに、実体喪失の認定は、具体的な事案の中で総合的に判断されており、また法律婚を破綻に導いた有責性も、考慮されない場合があるようです。