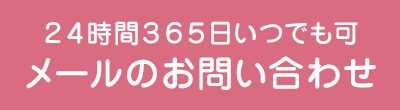婚姻法の内縁への類推適用婚姻の法文解説
本ページでは、婚姻についての法文を解説しています。離婚についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。
離婚・財産分与・慰謝料請求は、最低限の費用で済む当事務所へご相談ください。
内縁には、夫婦共同生活の実体が存在することより、共同生活にかかわる婚姻法の種々の規定が、類推適用されます。
次のような規定が、該当します。
- 同居協力扶助義務(第752条)
- 婚姻費用分担請求権(第760条)
- 日常家事債務の連帯責任(第761条)
- 夫婦財産の共有推定(第762条)
しかし、①に関しては、次のような判例があります。
内縁は、事実上の関係であり、当事者の一方が内縁継続の意思を失って別居し、共同生活の維持について協力をしない場合には、内縁は解消されたものと判断され、他方が、一方に同居協力請求をすることは、できません(名古屋高等裁判所決定昭和33年)。
②④は、現実の紛争形態としては、内縁解消後に、医療費や生活必要費を立て替えた側が、過去の婚姻費用として返還請求したり、財産の帰属を争う場合に、問題になります。
例えば、死亡した内縁の夫名義の不動産について、④を類推して、内縁の妻との共有と認定し、さらに出資額の割合で共有持分を認め、内縁の夫の相続人に対する、更正登記を認めたものもあります(東京地方裁判所判例平成4年)。
成年擬制(第753条)は、能力規定の画一的な扱いの必要性から、類推適用が否定されます。また、夫婦間の契約取消権(第754条)は、規定の不合理さから、内縁への類推適用は否定されます。
判例は、内縁が破綻する前に結ばれた贈与契約は、規定の不合理さだけでなく、内縁の妻には相続権がないことなど財産的保護が薄いため、第754条を類推適用すると、贈与を受けた内縁の妻の法的地位が、不安定なものとなり、不当な結果をきたすことも理由として加え、内縁破綻前に結ばれた契約についても、取消しができないことを明確にしました(高松高等裁判所判例平成6年)。
夫婦の氏(第750条)や、姻族関係の発生に関する規定(第725条)も、類推適用はされません。